学校コンサルで多い相談「どんな作業が合っているのか?」
Recently updated on 11月 27th, 2025 at 08:41 am
学校コンサルテーションで特別支援学校の先生方から寄せられたご相談のうち、今回は以下のご相談に対して提案した内容の一部を紹介いたします。
~先生からのご相談 ベスト3~
第2位「どんな作業が得意なのか?合っているのか?」
生徒の得意なことを見つけ、その能力を伸ばしていくことが理想的な指導ですが、中にはそれがなかなか見出せないケースがあります。
例えば、以前に次のようなご相談がありました。
『B君は手先がとても器用。しかし作業学習(※文末参照)では、すぐに飽きてしまい途中で作業を投げ出してしまう。B君の手先の器用さを生かすためには、どのような作業を設定すればいいのでしょうか?』
実際、B君に就労アセスメントを実施すると手先が非常に器用で幅広い作業種に対応できるスキルを持っていることが分かりました。
しかし一方で「継続力」「生産性」に課題が見られました。特に、同じ動きを繰り返す単調作業(ルーティンワーク)ではその課題が顕著に表れました。開始から間もなく、途端にペースが落ちてきて最終的には動きが止まってしまい、続行が困難になりました。
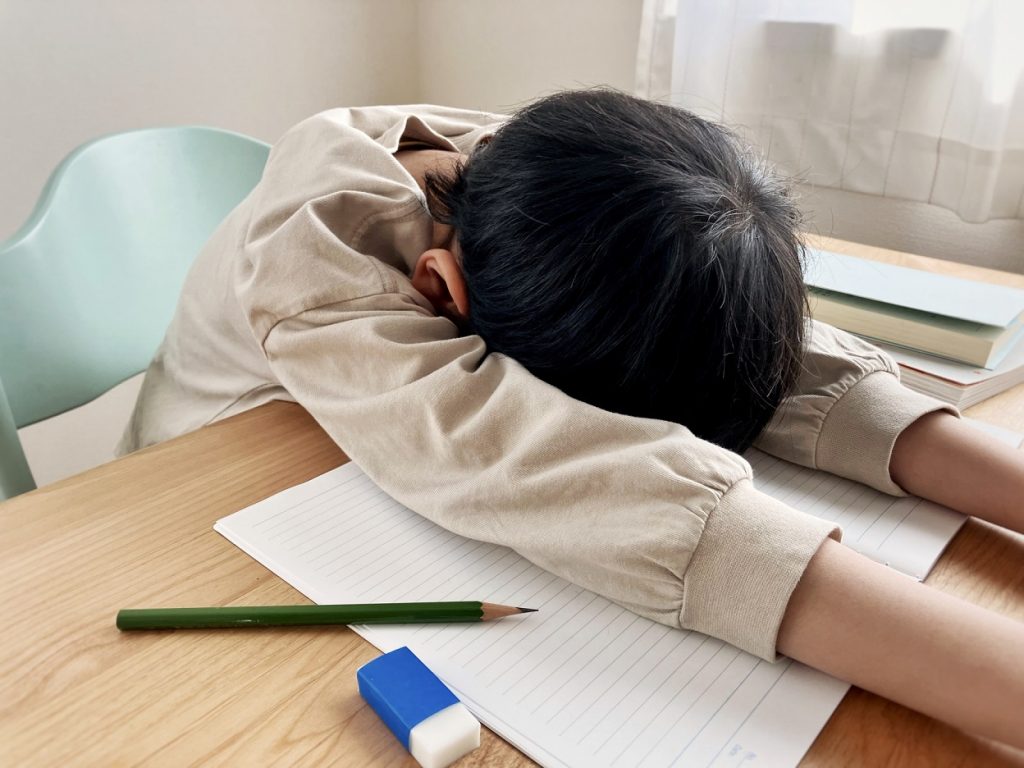
最後まで中断なくやり遂げられた作業もありました。カードを番号ごとに分類する・毎回提示されるお手本が変わるなど「その都度、判断を伴う作業」は集中が途切れることがありませんでした。
このようなB君の特性を生かし、作業学習の環境を設定していくことになりました。
まず先生方には、単調にならないような作業の切り出しを検討しました。B君はリサイクル班(ペットボトルの回収~洗浄~分類)に所属していましたので、ペットボトルの分類をこれまでよりも更に細かく分け、形状、容量、種類ごとに細分化した分類作業を新たに設定しました。また、飽きてしまう場合は作業を”ローテーション制”にして、数分ごとにタイマーを鳴らして作業を切り替え、従事時間を延ばすように工夫してもらいました。
その結果、ペットボトルの分類に集中して取り組むB君の姿が見られました。分類されたボトルは箱の中で整然と並べられており、手先の器用さは一目瞭然でした。それを周りから褒められることで嬉しそうな様子も見られ、「自己肯定感」「達成感」を感じていることもうかがえました。
ボトル分類の細分化は、本来のリサイクル作業には全く必要ない工程かもしれません。しかし、先生方が本人の得意を生かそうと柔軟に対応してくれたことで、生徒の成功体験に繋がったケースでした。
次回はコンサルで多い相談、第1位「指示が通らない!」についてご紹介します。
<※注釈>作業学習・・・特別支援学校には作業学習と呼ばれる、就労を模した作業(清掃、調理、オフィスワーク等)があります。作業を通じて職業生活や自立に必要な能力を養うことを目的に設定されています。











 就労支援
就労支援
 雇用コンサル
雇用コンサル
 直接雇用
直接雇用


