【CJコンサル活動報告:障害者雇用編】
”空気が読めない”は障害か?~自閉症スペクトラム障害と職場の社会性~
Recently updated on 11月 27th, 2025 at 08:40 am
CJコンサルでは、障害者雇用に関する様々な課題へのコンサルティングサービスをおこなっています。
今回は、その中でよくご相談いただく「自閉症スペクトラム障害(ASD)」の方が直面する職場での課題について考えていきたいと思います。
発達障害、特にASDの代表的な特性の一つに「社会性の障害」があります。
社会性とは、他者の状況や立場、気持ちを理解し、その場に合った言動を選択していく能力です。この社会性に困難を抱えることで、ASDのある方は職場でさまざまな対人関係の課題に直面することが多くなります。
職場で聞かれる「社会性の障害」に起因するエピソードをいくつかご紹介しましょう。
職場で生まれる「気が利かない」の誤解
<エピソード1:退勤のタイミング>
同じ部署の同僚が忙しそうに残業していたが、自身の業務は終わっていたため、特に声をかけずに定時で退勤した。翌日、上司から「協調性がない」と注意を受けた。
<エピソード2:暗黙のルールの失敗>
新人の頃、来客があっても誰も指示を出さなかったので、お茶出しをしなかった。後で先輩から「ああいうのは新人が率先してやるものだよ」と指摘され、驚いた。
<エピソード3:雑談の距離感>
同僚たちとの雑談中、自分では普通に話しているつもりでも、「話が長い」「しつこい」などと受け取られ、徐々に周囲から距離を置かれるようになってしまった。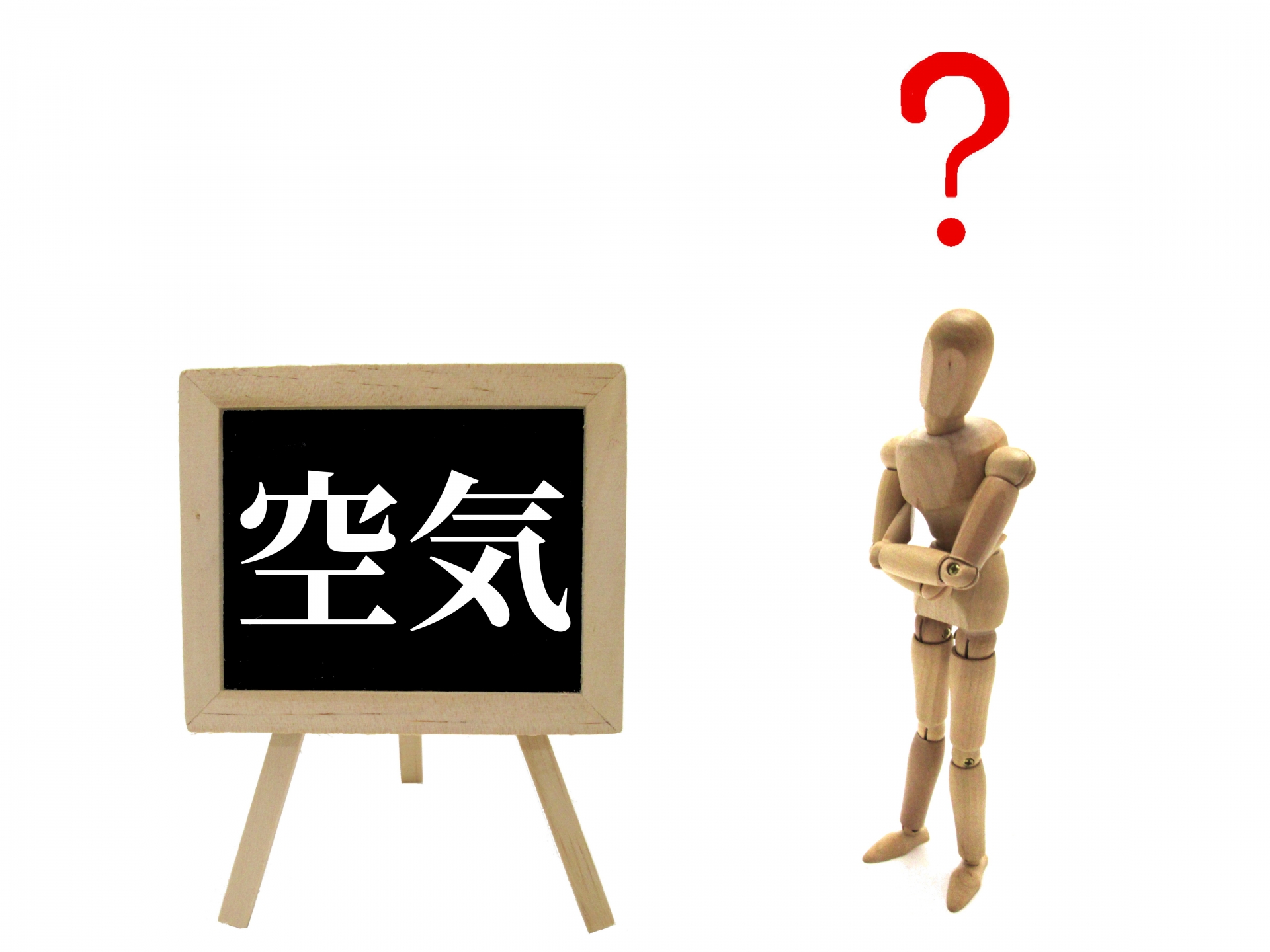
背景にあるASDの特性
これらのエピソードは、結果として周囲から「気が利かない」「空気が読めない」と評価されてしまう行動です。しかし、その背景にはASDの特性が隠れています。
エピソード1は、忙しい人の状況や気持ちを察するといった「共感性の困難」が招いた結果と考えられます。
エピソード2は、「お茶出しは新人がやるもの」という職場の暗黙のルールや文化を読み取ることが難しかったためでしょう。
エピソード3は、同僚たちの表情やトーン、ジェスチャーといった非言語情報の理解が難しく、会話の終わらせ時や相手の飽きに気づけなかった可能性があります。
これらの行動を「本人のやる気」や「性格」の問題として捉えるのではなく、その背景にある特性を理解することで、課題の見え方は大きく変わってきます。
企業としてできる歩み寄り
「社会性の障害」は、本人と周囲、双方が努力することで改善し、より良い関係性を築くことができます。企業としてできることは、まず環境の「見える化」です。
職場の暗黙のルールを明文化し、明確なマニュアルとして提示する:
本人へ話すときは、明確で直接的な表現を心掛ける。「察してほしい」は避けましょう。
ルールが必要な場合は、本人にとって分かりやすい基準を提示する:
例えば、「雑談は3分まで」「困ったら○○さんに声をかける」など。
私たちは、つい目に見える行動だけに着目して、「空気が読めない」「気が利かない」と評価してしまいがちですが、その背景にある障害特性に目を向けることで、相互理解のための対話が始まります。
障害特性に基づく行動は、単なる「性格」や「やる気」として捉えるのではなく、企業側は必要な環境整備のヒントとして、当事者側は”自身の課題”として捉え直すことで、双方が歩み寄り、働きやすい職場を互いに作り上げていくことへ繋がると考えます。











 就労支援
就労支援
 雇用コンサル
雇用コンサル
 直接雇用
直接雇用


